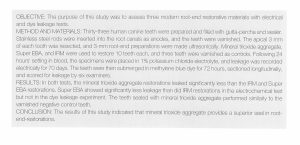アクアデンタルクリニック院長の高田です。
日本歯科麻酔学会から発表されている
「歯科治療中の血管迷走神経反射に対する 処置ガイドライン 」 を勉強しています。
ガイドラインの中の大切な内容をまとめながら、ブログに残していきたいと思います。
血管迷走神経反射に合併している循環器疾患と関連性はあるか?
不整脈などの循環器疾患を合併する場合、歯科治療中の血管迷走神経反射の発症頻度あるいは重症化に関連がある。
血管迷走神経反射の発症頻度あるいは重症化に循環血液量の減少を疑わせるような病態(貧血、低体重、低栄との関連はある。
心室性期外収縮を有する患者で、静脈内鎮静法のための静脈路確ー保時に血管迷走神経反射を起こし心停止に至ったが、
胸骨圧迫により拍動が再開し、回復後帰宅できたとの症例報告があり、
血管迷走神経反射による負荷が加わったため心停止に至った可能性が示唆され、
合併している循環器疾患と関連性が考えられる 。
献血者のバックグラウンドが血管迷走神経反射の発現に関連するかを検討する研究では、被検者 1,055 人の血管迷走神経反射の発生の献血者の中で、
循環血液量の減少が血管迷走神経反射の発生に関連があることが認められた 。
血管迷走神経反射に関する総説では、血管迷走神経反射を起こす患者の多くは、
交感神経系によって調節される正常な循環動態を示し、正常な圧受容体反射機能を有するとしている。
いくつかの症例では血圧の低下は心拍出量の低下や血管拡張に起因している。
血管迷走神経反射が重症化する因子としては、内臓循環や肺循環への血液貯留による体循環血液量の減少であるとされている。
交感神経系の虚脱による血管迷走神経反射では、徐脈を伴う血圧の低下が急激に起こり、意識消失は脳循環の虚脱に起因するため、徐脈性の不整脈などを合併している場合は、症状が重症化する危険性があることが示唆される。
左室機能低下例で血管迷走神経反射の関与が疑われる 2 症
例についての他の症例報告では、左室機能低下例に合併する神経調節性失神は難治性で予後の悪化に関連する可能性が示唆された 。
血管迷走神経反射は、体内の静脈系への血液の異常な貯留により体循環の血液容積が減少し、静脈還流が急激に減少した心室が交感神経反射が起きた時に症状が重症化する危険性がある。
また、一過性に心拍出量が減少するため、循環血液量の減少がある場合は、症状が重症化し、遷延化する危険性がある。
血管迷走神経反射は、体内の静脈系への血液の異常な貯留により体循環の血液容積血管迷走神経反射や失神の治療に用いた薬物の効果を論じた文献は多いが、一定の見解は得られておらず、国内外のガイドラインにおいても強く推奨されている薬物は存在しないようである。
誘因となる薬物の記載はあるが、その根拠となる文献は少なく、検索の結果、
該当する文献もなかった。また、VVR を前投薬で予防しうることを記載した文献はなかった。
治療前の血圧・脈拍測定で反射発現を予測できるか?
反射発現前には頻脈になるとの報告がある 。また、処置前の収縮期血圧が100mmHg 未満、
拡張期血圧が 70mmHg 未満で反射発現のリスクが低かったとの報告もある。
しかし、歯科治療中のどの処置が反射発現の引き金となるか一概にはいえないため治療前の血圧・脈拍測定で予測することは難しい。
ただ、反射発現の状態把握、迅速 に対処するためには持続的な血圧・脈拍測定は有効である 。
血管迷走神経反射は様々なことが原因で発症する。反射発現前には頻脈になるとの報告があるが、例えば歯科治療中における局所麻酔施行後、患者は注射による痛みと局所麻酔薬内に含まれる
血管収縮薬により血圧と脈拍の上昇がみられる。
しかし、その後全ての患者が反射を発現するわけではない.
また、血圧においても処置前の血圧が低い方が反射発現のリスクが低いとの報告があるが、高血圧症を有する患者はもともとの血圧が高くどこに基準を設けたらいいか不明瞭である。
以前にも反射発現の既往があること、治療当日の体調、年齢、性別など様々な因子を考慮する必要がある。
さらに歯科治療中患者の状態は刻々と変化しどの処置が反射発現の引き金になるか一概にいうことができない。
そのため治療前の血圧・脈拍測定のみで反射発現を予測することは難しい。
しかし、治療前より血圧・脈拍などのバイタルサインを持続的に測定することは血管迷走神経反射などの偶発症を速やかに発見し対処することができるため重要と思われる。